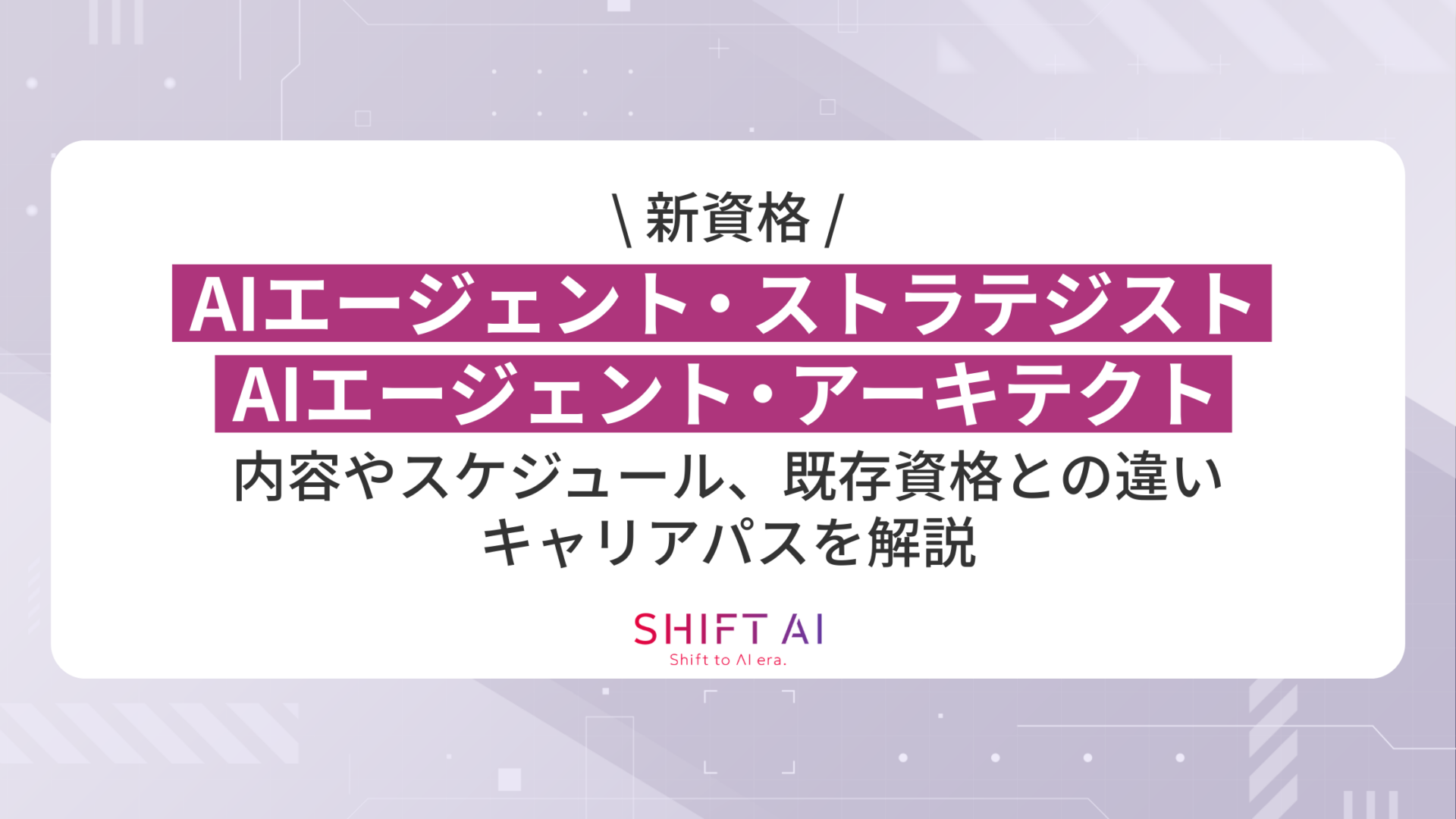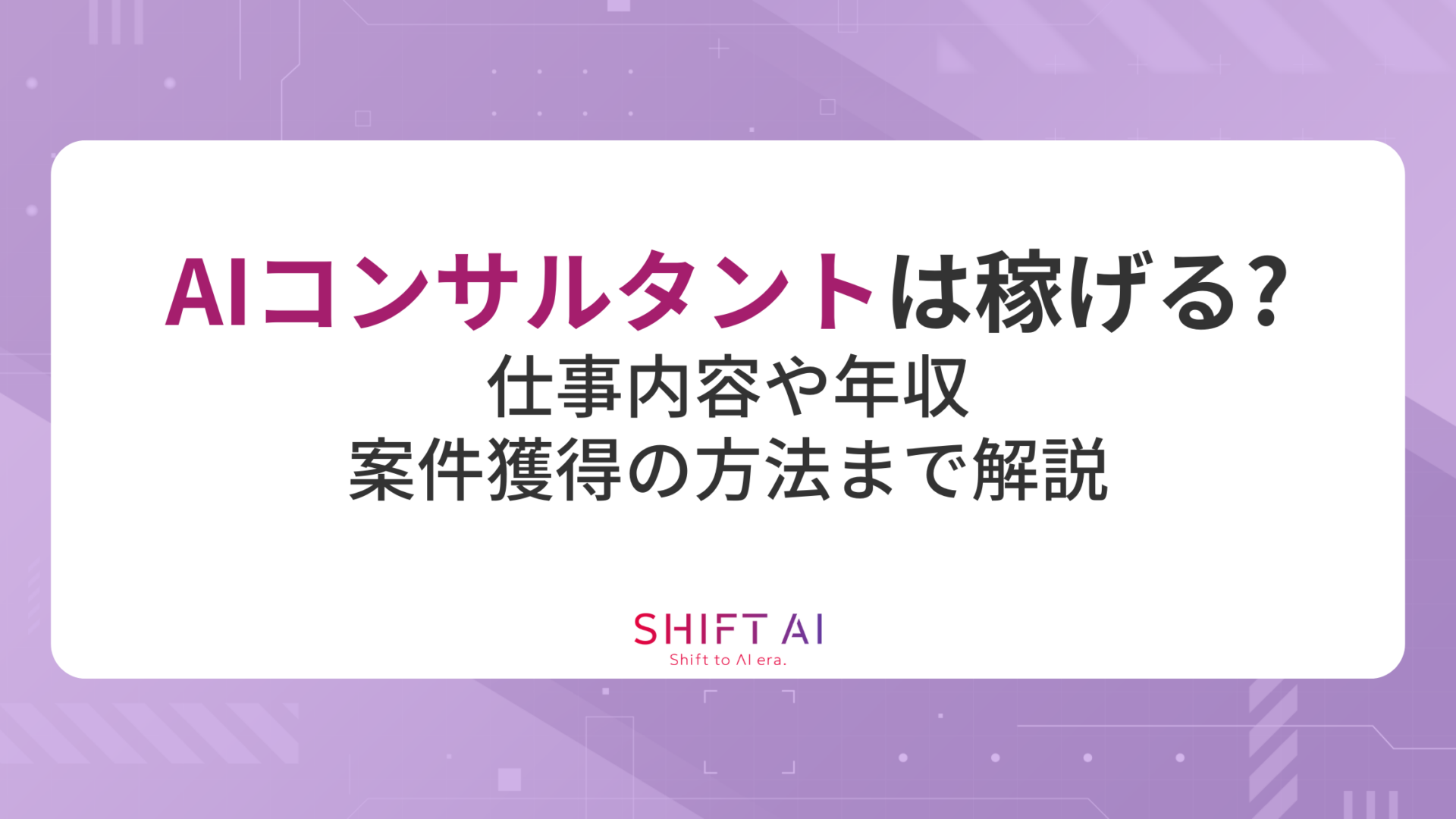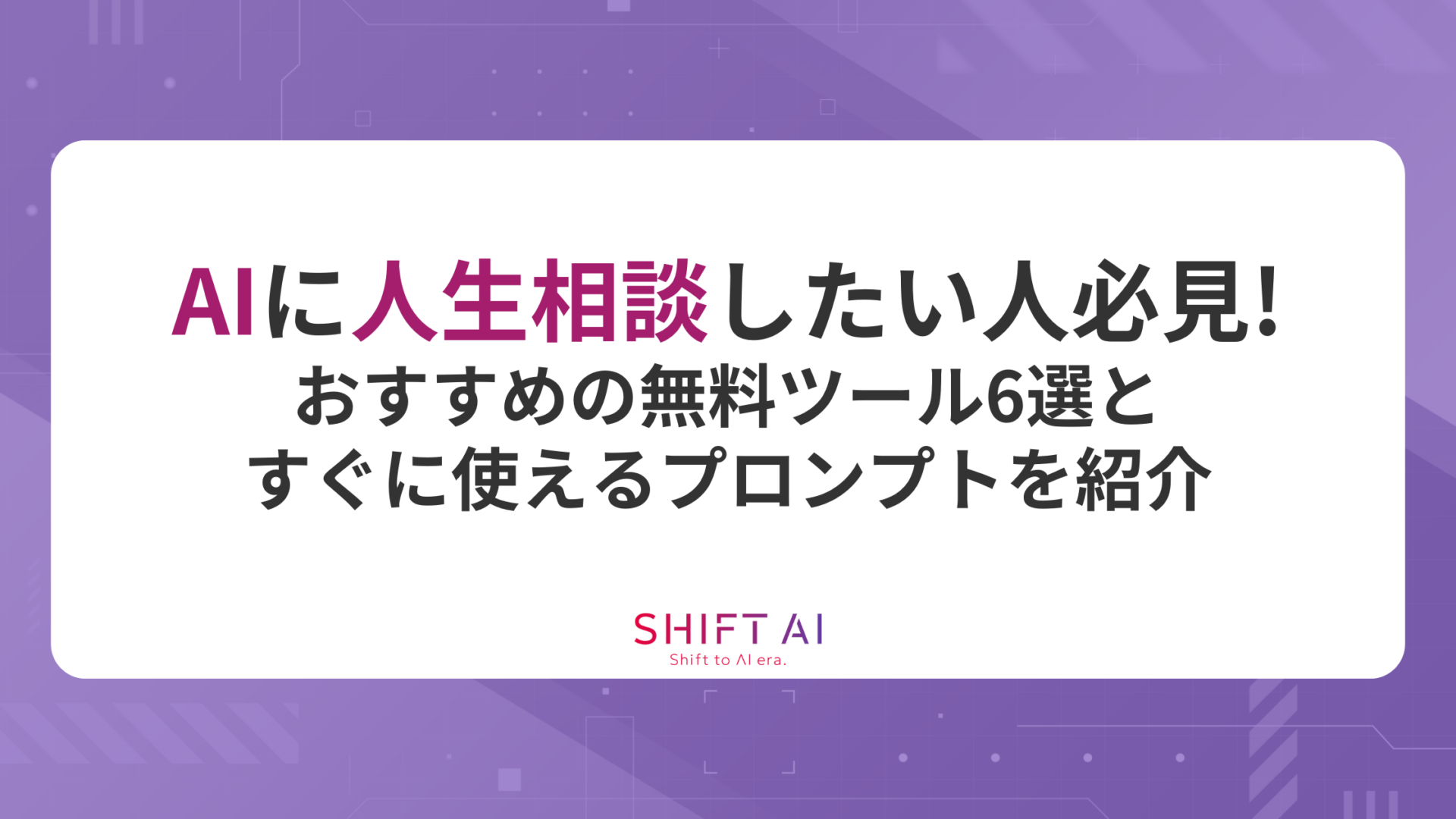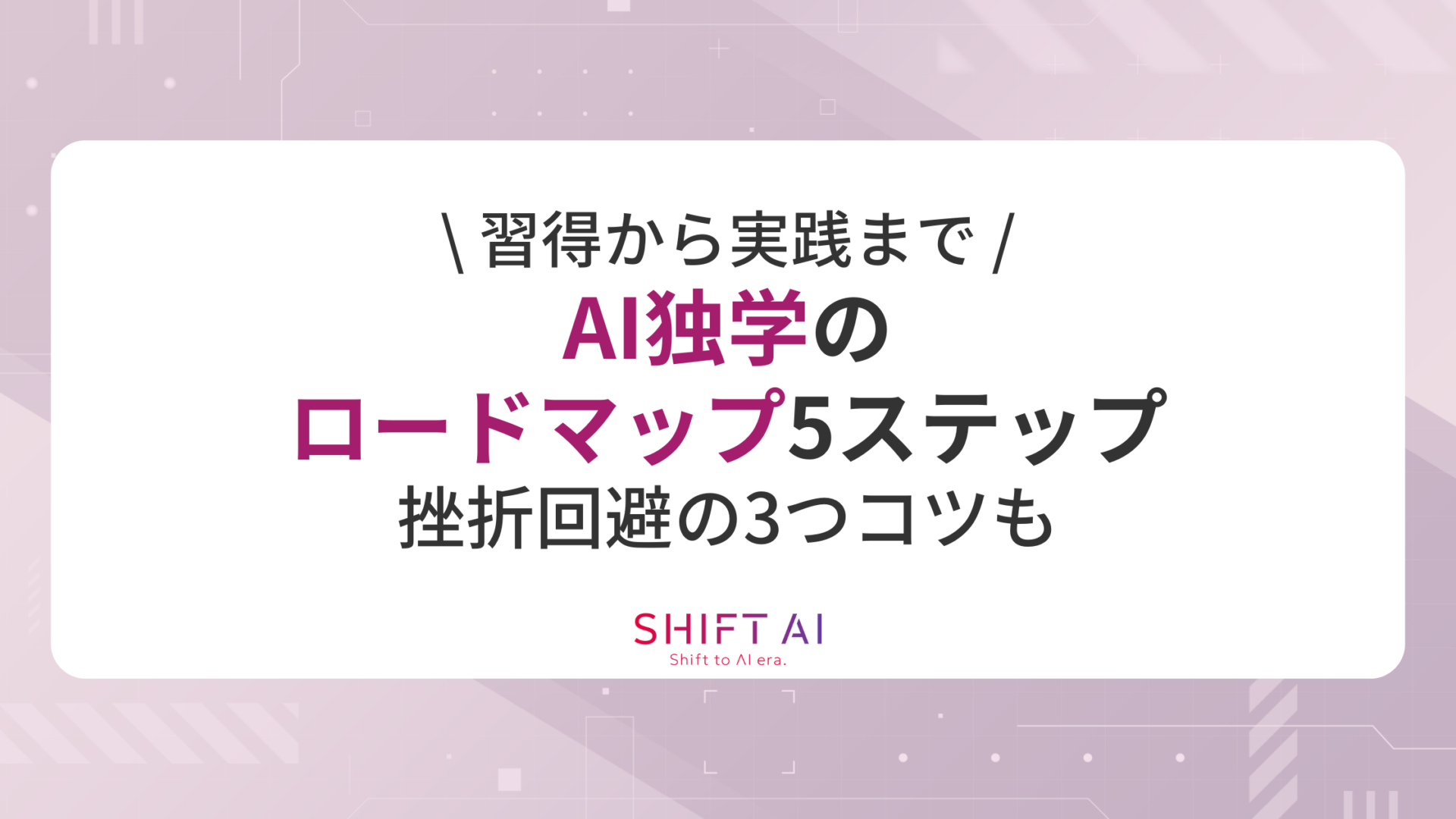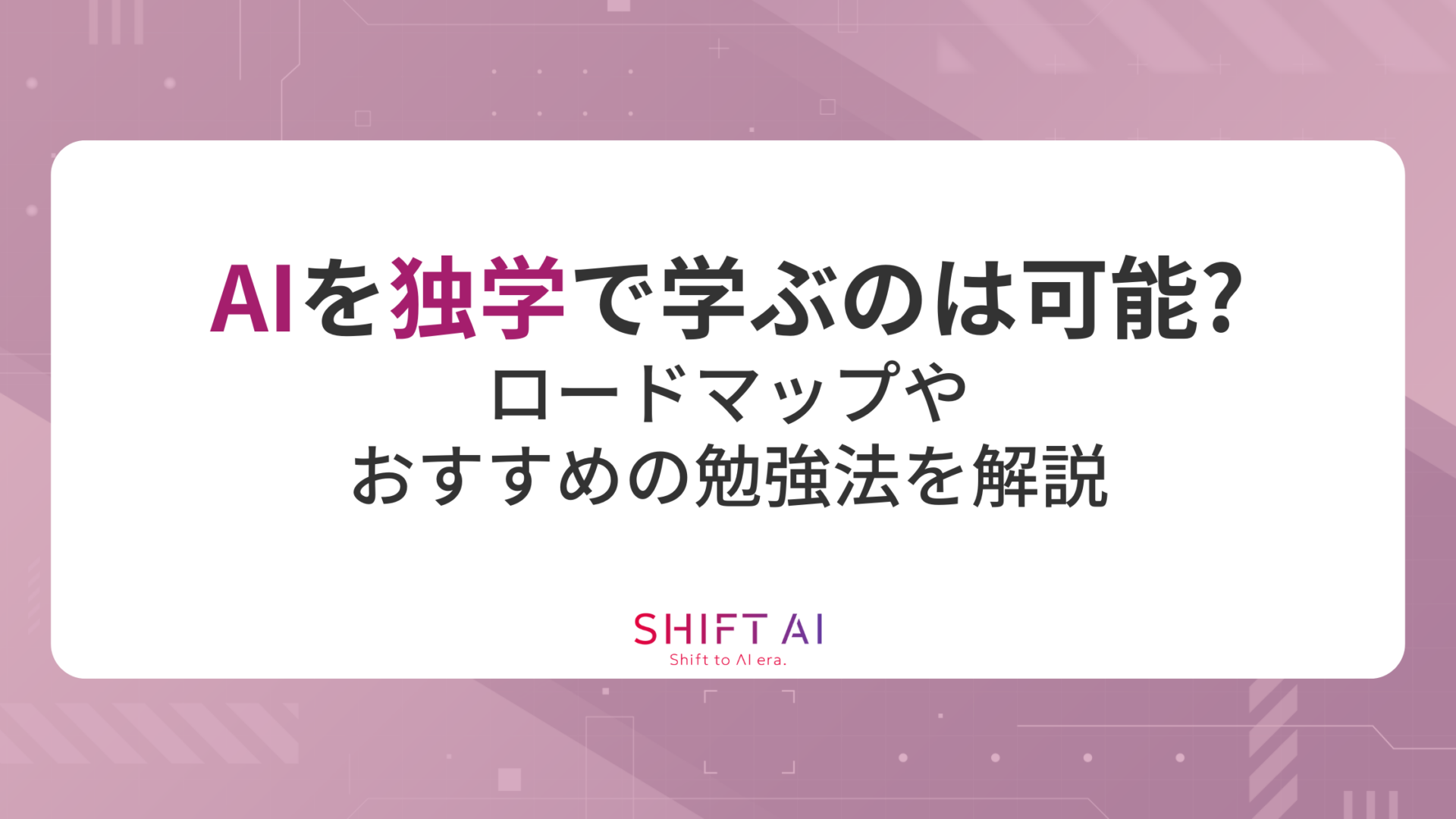年平均成長率23.4%、205億ドル市場へ──AI漫画が切り拓く創作の新時代
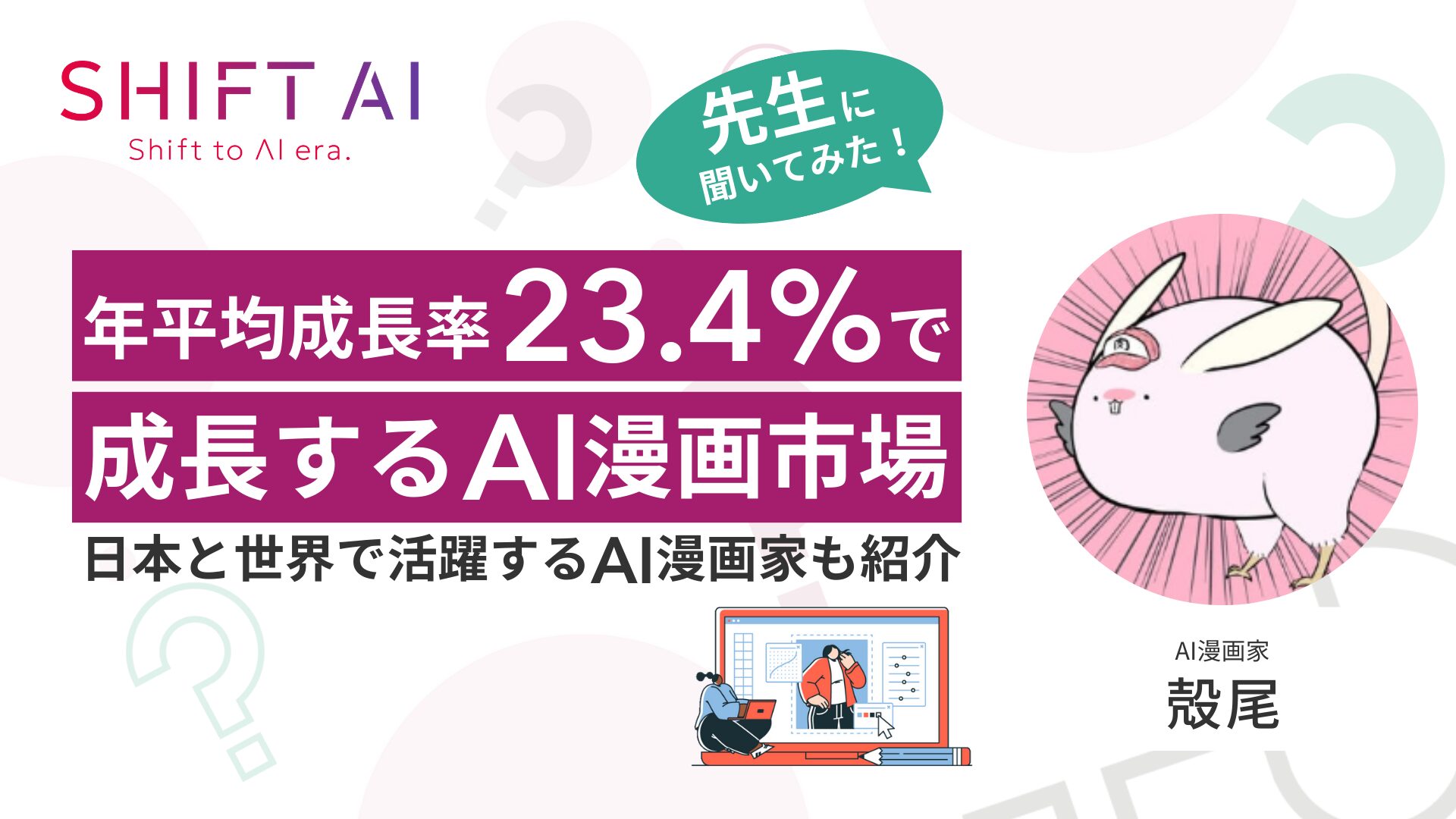
「AI」と聞くと、どこか難しくてとっつきにくい印象を抱く人も多いかもしれません。しかし実際には、AIは私たちの日常のさまざまな場面で応用されており、創作の世界でもその活用が進んでいます。
記事の前編では、AI漫画家の殻尾さんに、AI漫画の制作方法や文化的影響についてうかがいました(下記リンク参照)。
本稿・後編では、成長を続けるAI漫画市場の概観とともに、日本や海外で活動する注目のAI漫画家たちをご紹介します。多様化する創作スタイルの最前線にも迫ります。
目次
プロAI漫画家が続々誕生?2034年、AI漫画市場は205億ドルへ
アメリカの調査会社Market.USによると、2024年のコミック生成AI市場は約25億ドルに達し、2034年にはおよそ205億ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は23.4%という驚異的な伸びです。
AI生成コミックの成長をけん引しているのは、こうしたコンテンツに柔軟なストーリー設計やキャラクター構築を可能にする技術力と、多様なニーズに応えるパーソナライズ性があるからです。北米では約43%の売上シェアを占め、10億ドル超の規模を誇ります。
世界のコミック生成AI市場の成長予測
画像出典:https://market.us/report/ai-comic-generator-market/
収益モデルの主流は、月額制のサブスクリプション型サービス(全体の57.7%)。価格帯の選択肢が広く、継続しやすい点がユーザー支持につながっています。
また、ユーザーの42.6%を占めるのは、企業に属さず趣味や創作活動として漫画を制作する個人クリエイター。参入障壁の低さと制作コストの安さから、今後さらに個人ユーザーの増加が見込まれています。
日本では、もともと同人文化が盛んな背景もあり、趣味でAI漫画を制作する層が市場を支えています。今後は、そうした個人ユーザーの中から「プロAI漫画家」が続々と誕生する可能性もあるでしょう。
AI漫画家として異例の快挙。Rootport氏、TIME誌の「AI 100」に選出
日本のAI漫画家を語るうえで欠かせない人物の一人が、Rootport氏です。同氏は2022年8月10日、画像生成AI「Midjourney」のオープンベータ版が公開されて間もない時期に、AI漫画『サイバーパンク桃太郎』の冒頭をXに投稿しました。
桃太郎という日本人にとって馴染み深い昔話を、SF的な世界観で再構築したこの作品は、画像生成AIの可能性を探る試みとして瞬く間に注目を集めました。
その後、電子書籍および書籍としても出版され、先駆的なAI漫画のひとつとして高く評価されるようになります。
Rootport氏の取り組みは海外でも注目を集め、2023年には、TIME誌が選ぶAI分野の注目人物100人「TIME AI 100」に選出されました。
政策シンクタンクでも注目。小沢高広氏が語るAIと漫画の未来
個人の取り組みに加えて、政策レベルでもAI漫画への関心が高まっています。
政策シンクタンクである独立行政法人・経済産業研究所は、2024年3月8日に開催した講演会「漫画制作における生成AI活用の現状:2024春」の資料を公開。
この講演では、漫画家ユニット「うめ」でシナリオ・演出を担当する小沢高広氏が登壇し、AIを活用した漫画制作の現状と今後の展望について発表し、「生成AIが漫画家の仕事を奪うのではないか」という懸念にも言及がありました。
小沢氏によれば、少なくとも短中期的には、生成AIによって漫画家の仕事が奪われる可能性は極めて低いと言います。
むしろ、生成AIはプロの作業効率を高める一方で、アマチュア漫画家の裾野を広げることで、結果的に漫画文化の多様性を押し広げるだろうと予想されています。
AI画像は著作権NG?著作権局が下した判断とは
世界のAI漫画家を語るうえで欠かせない作品のひとつに、アメリカのクリエイター、クリス・カシュタノヴァ(Kris Kashtanova)氏による『夜明けのザーリャ(Zarya of the Dawn)』があります。
Midjourneyを用いて制作された本作は、2022年9月、画像生成AIの使用を伏せたまま、アメリカ著作権局に著作権登録の申請が行われました。
『夜明けのザーリャ(Zarya of the Dawn)』表紙
画像出典:https://www.kris.art/portfolio-2/project-one-ephnc-jamy8
当初は著作権保護が認められていましたが、画像生成AIの使用が判明したことで、アメリカ著作権局は一転して登録を取り消しました。
その後、2023年2月、著作権局は漫画作品におけるテキストやキャラクターの配置には著作権保護を認める一方、生成AIによって作られた画像自体には著作権は認められない、との判断を示しました。
この事例は、画像生成AIコンテンツの著作権をめぐる課題を浮き彫りにした、最初期のケースのひとつと言えるでしょう。
絵が描けなかった57歳が叶えた夢。AIが拓く“もうひとつの創作人生”
クリエイター向けメディア「Muse by Clios」は、2022年9月にAI生成コミック『サマーアイランド(Summer Island)』を紹介する記事を公開しました。
この作品を手がけたのは、コンテンツ制作会社Campfireのクリエイティブディレクター、スティーブ・コールソン(Steve Coulson)氏です。画像生成AIが登場して間もない時期に制作され、注目を集めました。
当時57歳だったコールソン氏は、5歳の頃からコミックを読み続けてきた生粋のファンでしたが、絵が描けないことを理由に、自作のコミックを発表することはありませんでした。
しかし、画像生成AIの登場により、ついに長年の夢だった自身のコミック制作を実現します。
『サマーアイランド(Summer Island)』の1ページ
画像出典:https://musebyclios.com/digital-data/creative-director-and-ai-made-comic-book-together?utm_source=chatgpt.com
コールソン氏は、プロンプト入力だけで制作するという方法を採用し、画像を大量に生成した後、それらにインスパイアされながら物語を構築するという、いわば“トライ&エラー型”のアプローチをとりました。
この経験から氏は、「画像生成AIは、コミックの歴史を“登場以前”と“登場以後”に分けるほどの革命的なツールである」と語っています。
編集後記
CGがアニメ制作に浸透したように、生成AIも漫画制作における身近なツールになる日はそう遠くないでしょう。
とはいえ、著作権や学習データの扱いなど、技術だけでは解決できない課題も多く残されています。
AIで漫画を描くのが当たり前になったとき、人の手で描かれた漫画の価値が、あらためて見直される──そんな時代が来るのかもしれません。
執筆:吉本幸記
編集:中田順子