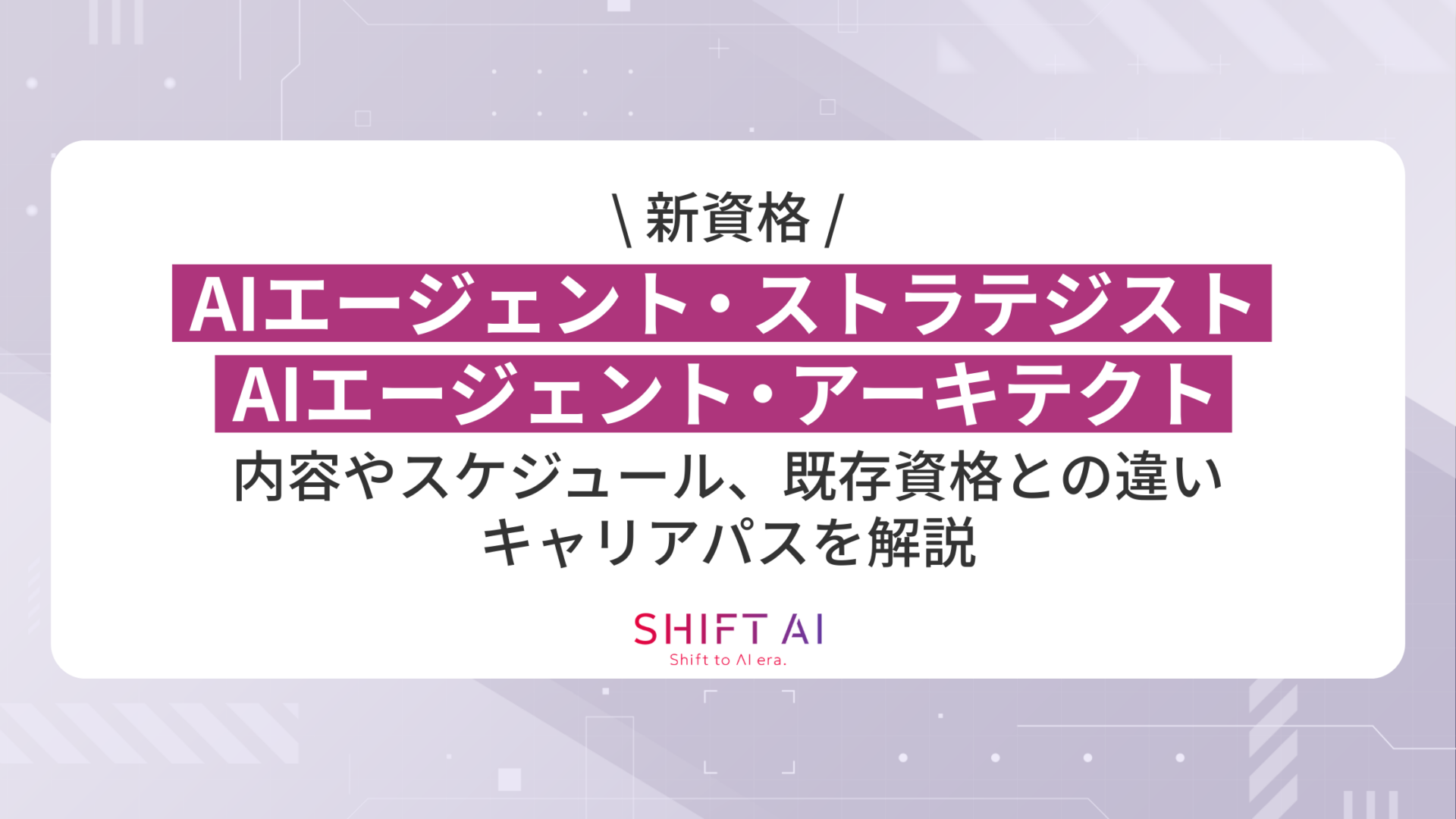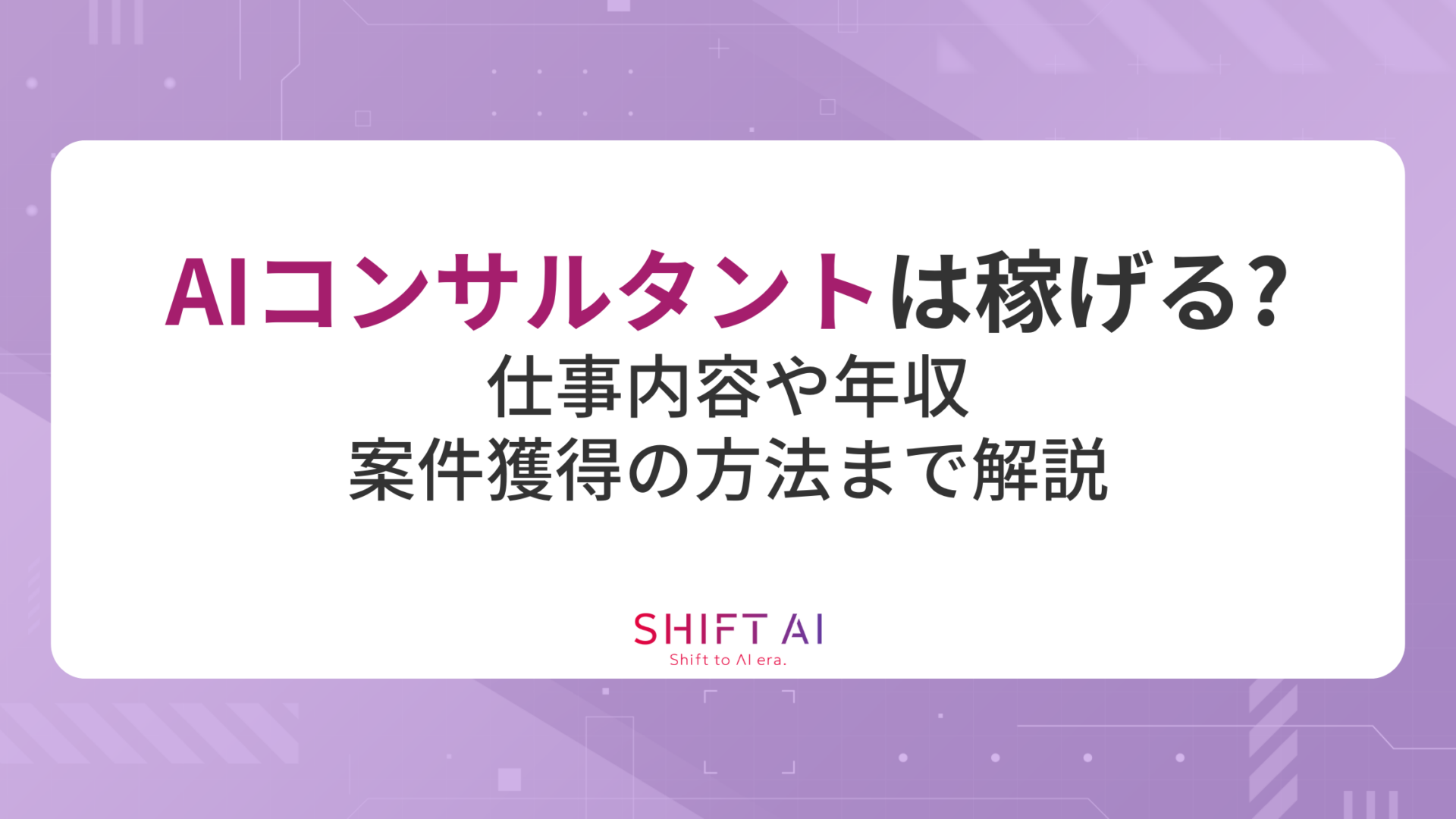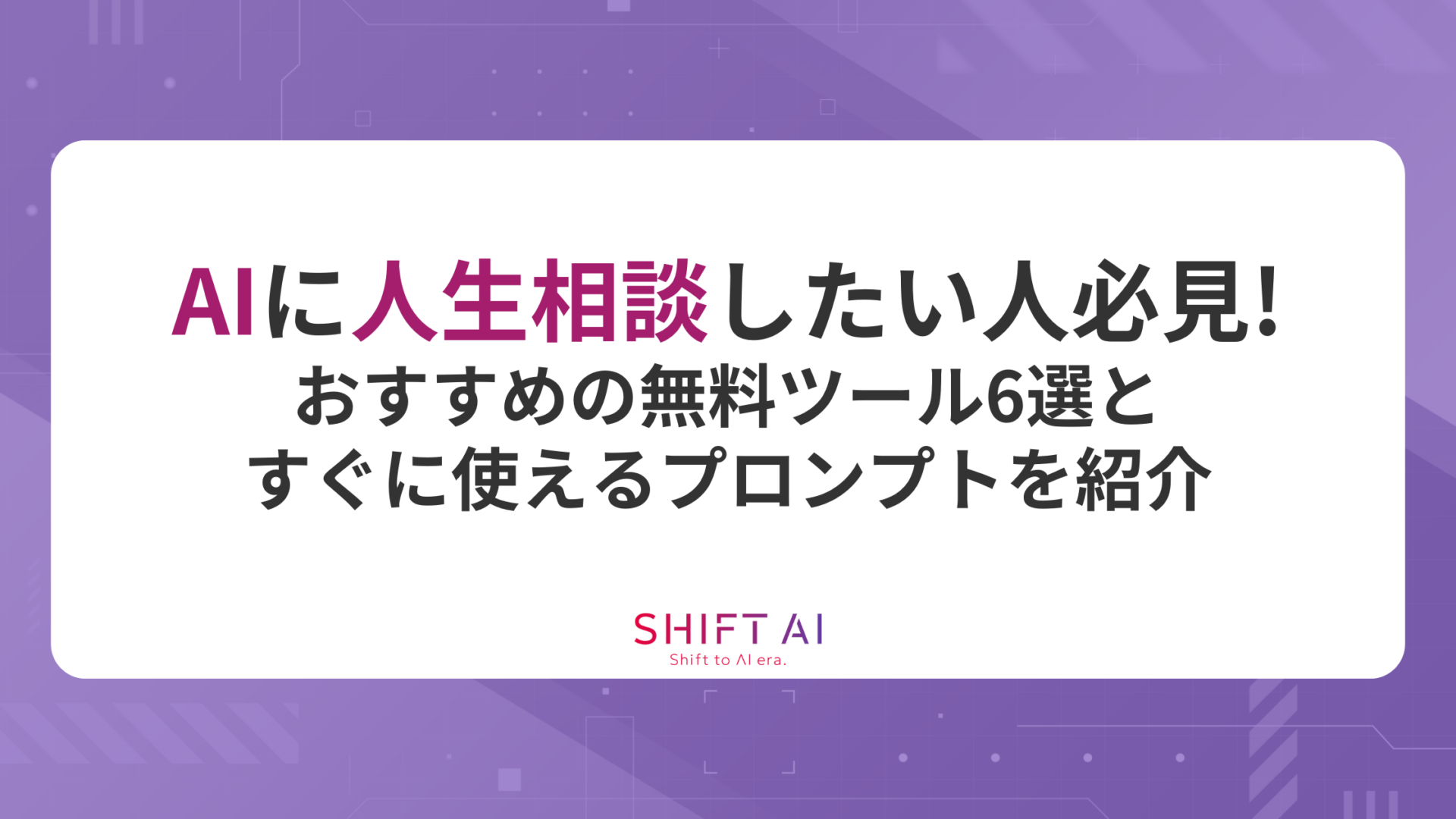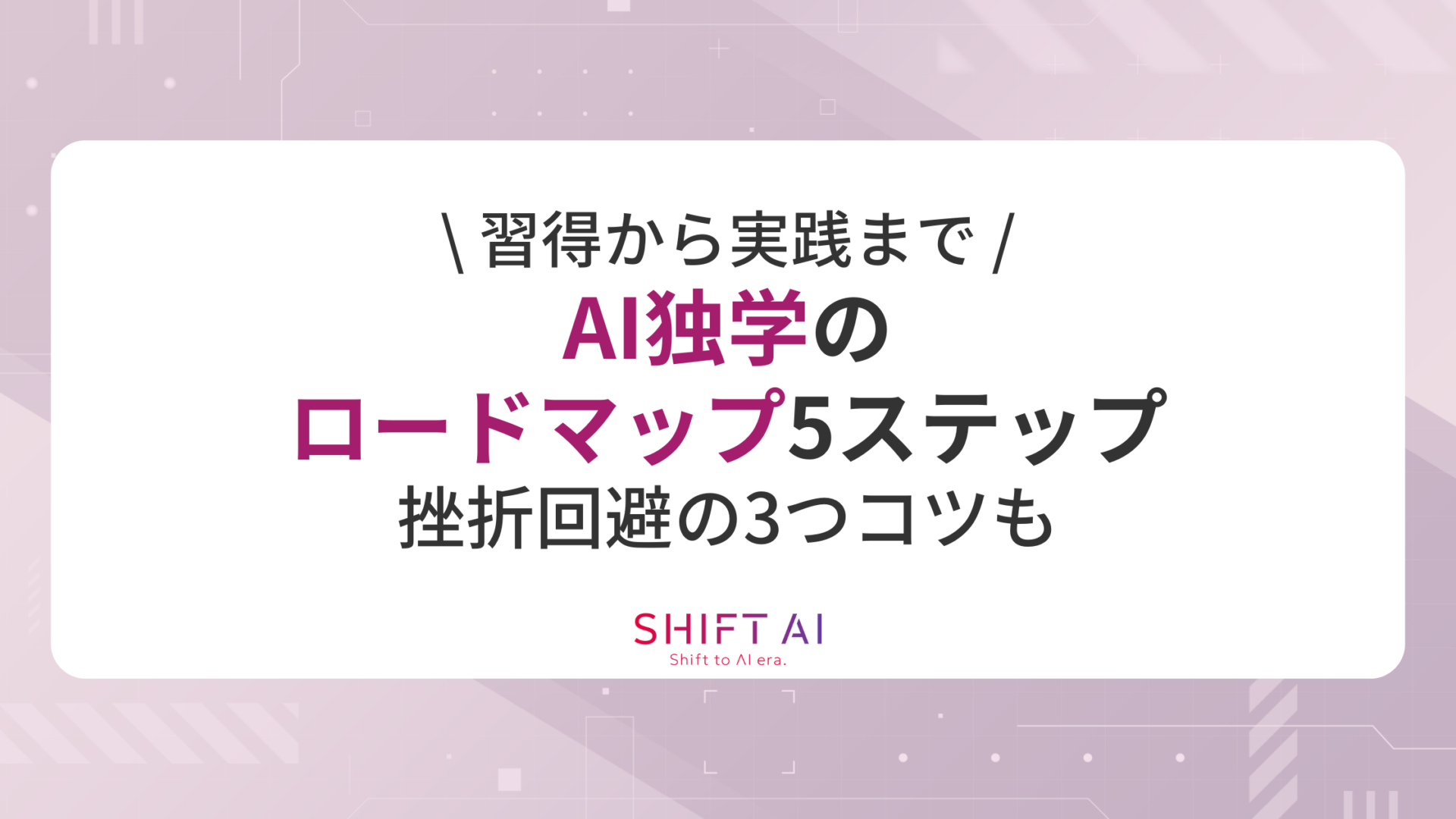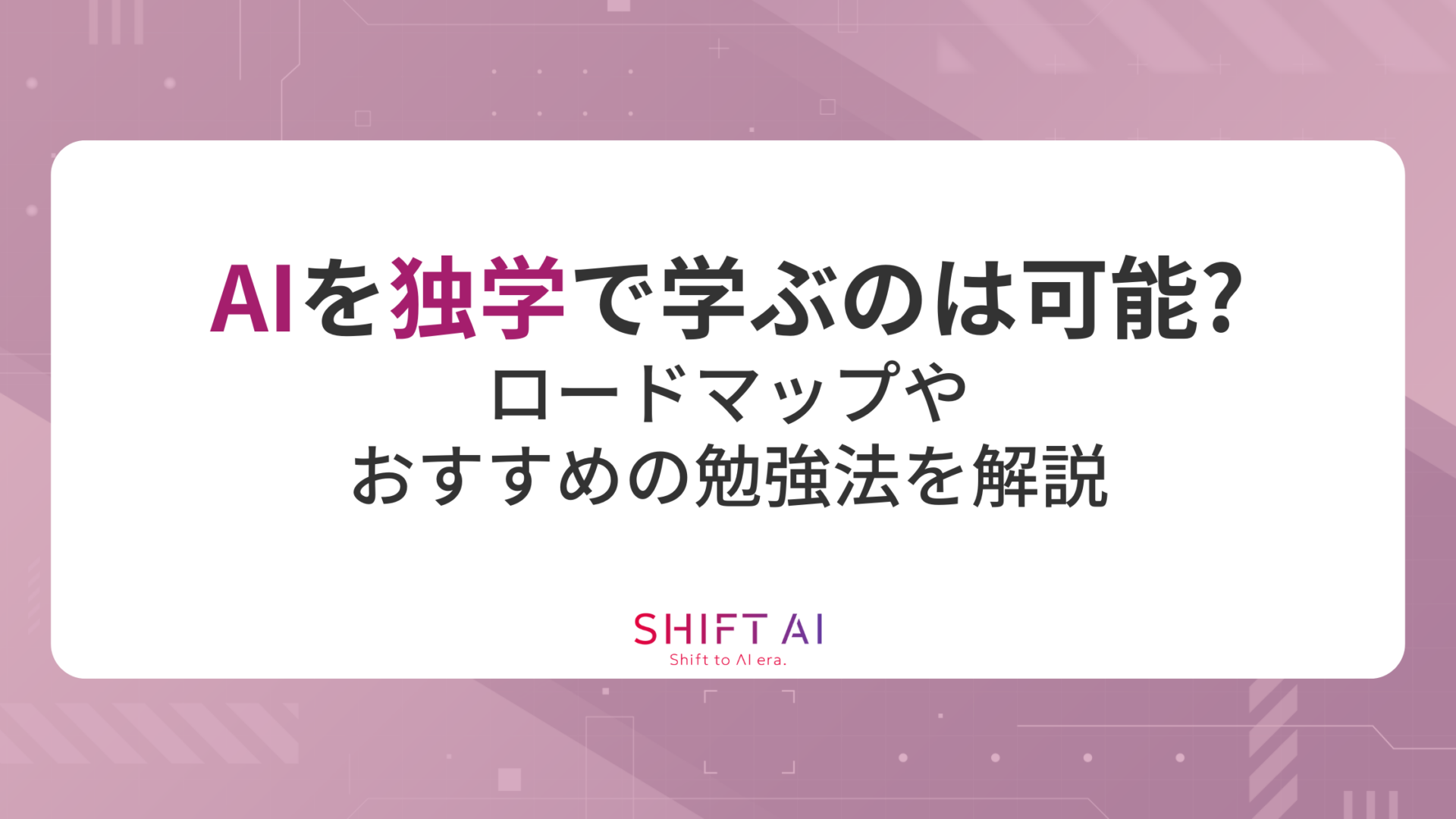AIが手塚治虫を超える日は来るのか──技術と物語が交わる「AI漫画」の最前線
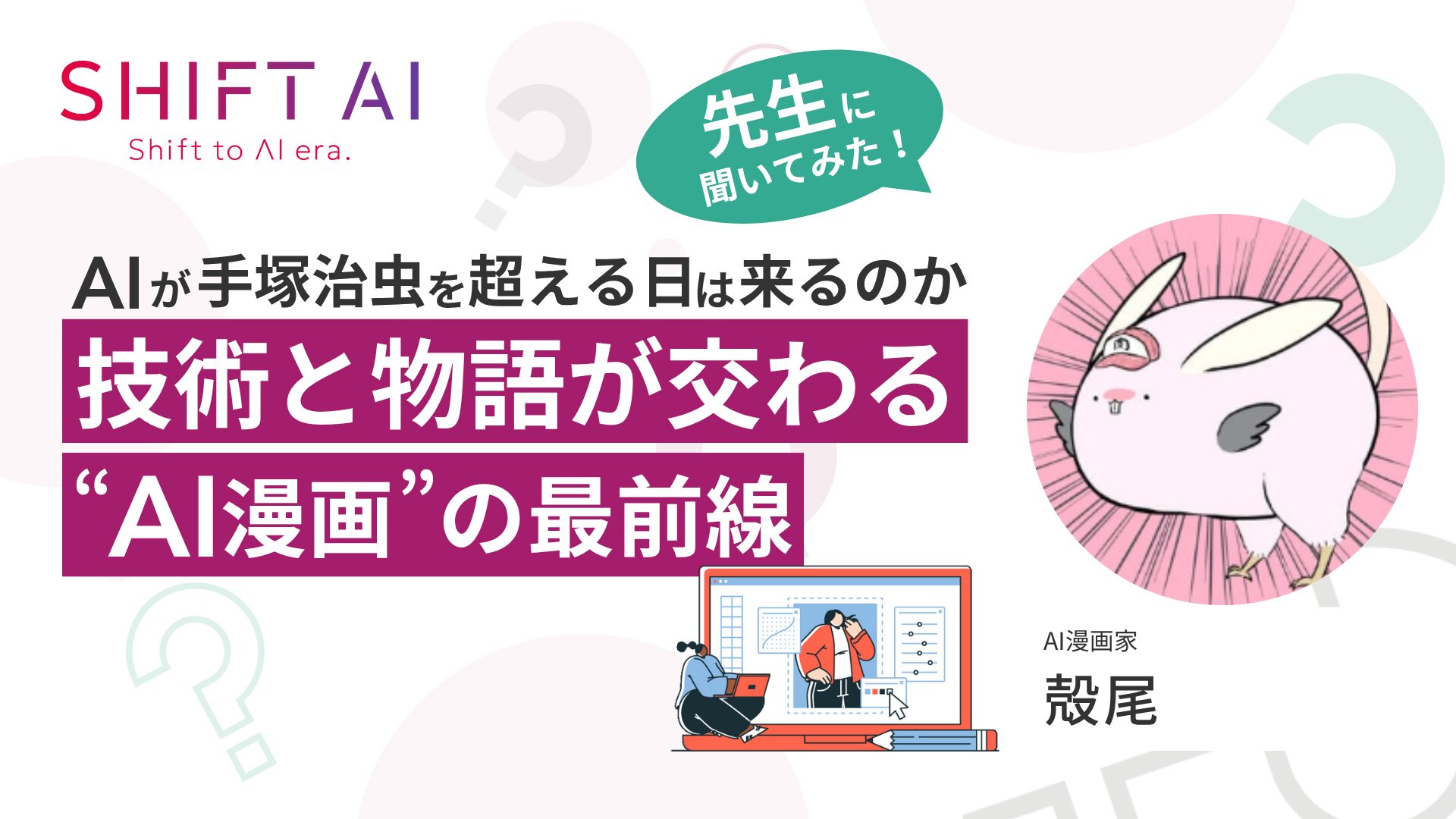
「AI」と聞くと、どこか難しそうで、とっつきにくい印象を持つ方も多いかもしれません。しかし、いまやAIは、私たちの日常のさまざまな場面で活用されるようになりました。
今回は、そんなAIの活用シーンの中でも「AI×漫画」にフォーカス。SHIFT AIでAI漫画コースの講師を務める殻尾さんに、気になる質問をぶつけてみました。
「AIは、手塚治虫や大友克洋のような“漫画の巨匠”になれるのでしょうか?」
近年、AIを取り入れた漫画制作や創作活動が広がりを見せています。
そんな中、従来の漫画家とは異なるキャリアを歩んできた殻尾さんの取り組みには、これからAI漫画に挑戦したい人にとって、大きなヒントが詰まっていると考えます。
本記事では、殻尾さんが語るAI漫画制作のプロセスや、AI漫画文化のこれからの展望について紹介します。
目次
機械エンジニアからAI漫画へ。異色のキャリアが生んだ新たな創作法
──はじめに殻尾さんの経歴を簡単に教えてください。
殻尾:もともと機械エンジニアとして宇宙産業に携わり、人工衛星の動作試験などを担当していました。その後、30代後半で脱サラし、イラストレーターに転身。
イラストレーターとして、ゲーム業界のイラスト素材案件を受注していました。その後、ウェブトゥーンの制作を経て、画像生成技術に軸足を移し、AI漫画を制作するようになりました。
創作活動自体は、専門学校でCGを学びながら趣味で絵を描いていたので、もう20年ほどになります。
──「AI漫画制作のプロセス」は、シナリオ作りと作画に分けられると思いますが、「シナリオ作り」ではどのようにAIを活用していますか?
殻尾:実は、2018年頃からゲーム業界でシナリオライターもしていたので、AIなしでもストーリーを組み立てるのは慣れているんです。
それでも現在は、発想を広げるためにAIを取り入れるようにしています。たとえば「特定のファンタジー世界の設定でストーリー案を提案してください」とAIに尋ねて、アイデアを引き出しています。
──殻尾さんのnoteに掲載されている『AI漫画【再誕のエルゴ-1】』のシナリオ作りは、AIをどのように活用しましたか?
殻尾:NovelAIという執筆支援ツールを使っています。このツールでは、ボタンを押すとAIが数行単位で文章を出力してくれます。大まかな世界観は自分で入力し、あとはプロットなしでもAIがストーリーの断片を書き進めてくれる感じです。
たとえば、私が「生まれる前、世界はもっと違う感じだった。見渡す限り山のようなビルが並ぶ、空は大きなホバーシップで埋め尽くされていた」と入力すると、続きの文章が自然に書き進められます。
AIの出力は後から修正可能なので、必要に応じて校正しています。こうして、ボタンを押して出てきた文章を自分で加筆して、ストーリーを完成させました。まるでAIとリレー小説を書いているような感覚ですね。
ChatGPTとNovelAIで進化するシナリオ制作
殻尾:ChatGPTを使うと、NovelAIよりも大量の文章が生成できます。しかも、その出力された文章は整合性が取れており、たとえば「キャラクターBを追加してください」と入力すると、入力内容に沿った別パターンのストーリーが出力されます。
私はChatGPTを使う際、NovelAIも併用しています。最初にNovelAIでおおまかな文章を生成し、その後、その文章をChatGPTに入力するんです。こうして、ある程度の世界観や設定を固めたうえで、ChatGPTにアイデアを提案させています。
──シナリオ作りに生成AIを活用することで、どんなメリットを感じていますか?
殻尾:生成AIを使うようになって、シナリオを練り上げるスピードがぐっと上がりました。一人で考えていると、どうしても展開が似てきてしまうのですが、AIにアイデア出しをさせることで、自分では思いつかないような展開も取り入れられるようになったんです。
──作画に入る直前のシナリオは、どのような形で仕上がっているのでしょうか?
殻尾:私の場合、作画にはストーリープロットをもとに取りかかります。これは、人物の細かな動きや場面の状況を、時系列で整理したものです。ChatGPTが出力したストーリー構成をベースに、それをさらに詳細化していくイメージですね。
──ストーリープロットの1行が、漫画の1コマに対応しているのですか?
殻尾:1行が必ずしも1コマに対応しているわけではなく、1行で2コマ、3コマ分の場面を説明していることもあります。
AIツールを駆使した創作の舞台裏と、乗り越えるべき壁
殻尾:ストーリープロットが完成したら、次はネームを書きます。ネーム作成では、画像生成AIを使わず、すべて手書きで行います。ネームでは、コマ割りや絵の配置をスケッチ風に書いていきます。この段階では、かなりラフな状態(下記画像参照)でも問題ありません。ネームが完成した後に、画像生成AIを使って、各コマごとの絵を生成します。
──画像生成AIには、どのようなツールを使っていますか?
殻尾:基本的にはStable Diffusionです。デザインにこだわりたい小物を生成する際には、Midjourneyを使うこともあります。最近では、ChatGPTの画像生成機能も活用していますね。
──【再誕のエルゴ-1】の表紙に描かれたビル群は、どのように作ったのですか?
殻尾:これは、生成AIを使って完全に出力したものです。次のページにある4つのコマも、それぞれ生成AIを使って一発で出力しています。
キャラクターと背景を別々に生成し、レイヤーで合成しているコマもあります。たとえば『AI漫画【再誕のエルゴ-2】』の最初のコマでは、手前のキャラクターと奥にいる女の子を別々に生成し、レイヤーで重ねて仕上げています。
──先ほど「デザインにこだわりたい小物はMidjourneyで生成する」とおっしゃっていましたが、具体的にはどんな例がありますか?
殻尾:【再誕のエルゴ-2】に登場する、望遠鏡で空中要塞をのぞいているコマがそうです。このシーンでは、望遠鏡の先に浮かぶ空中要塞を描く必要があったのですが、Stable Diffusionではうまく表現できなかったため、Midjourneyを使って生成しました。
──画像生成では、限界を感じるような漫画表現もありますか?
殻尾:はい。少年漫画でよく使われる、パースの効いた勢いや動きのある絵は、うまく生成できません。武器や服装に関しても、ゲーム業界で見られるような凝ったデザインと比べると、やはり見劣りします。こういった表現は、プロンプトを工夫しても、満足のいく出力にはなかなかならないですね。
──キャラクターの動きに合わせて、自然で矛盾のない姿勢を描く必要もあると思います。こうした“姿勢制御”の課題には、どう対応していますか?
殻尾:Stable Diffusionの拡張機能「ControlNet」を使っています。最近では、ChatGPTでもポーズの指定ができるようになってきました。たとえば女の子の画像をChatGPTに入力し、そこに3Dモデルを組み合わせて「このポーズにして女の子の画像を生成して」と指示すると、指定した姿勢の画像が出力されるようになります。
AI漫画からメガヒットは生まれるのか?
──10年、20年という長いスパンで見たとき、人間が簡単な入力をするだけで、手塚治虫や大友克洋のような長編漫画を生み出せるAIが登場する可能性はあると思いますか?
殻尾:10年や20年のうちに、そうしたAIが誕生する可能性は、限りなく低いでしょう。技術的なハードルもありますが、それ以上に、著作権などの法的・社会的な課題が大きい。たとえば、そうしたAIを開発したとして、出版社がお金を出すのかどうかも疑問です。
ただ、私のようにAIを活用しながら漫画をつくる作り手が増えていけば、AI漫画の中からメガヒット作が生まれる可能性は十分あると思っています。そうした作家が「漫画界の巨匠」と呼ばれる未来は、現実味があるかもしれません。
──今後、AIを活用するクリエイターが増えることで、漫画やアニメなど各ジャンルの創作に広がりが生まれていく、という理解でよろしいでしょうか?
殻尾:まさにその通りです。AIによって技術的なハードルが下がることで、これまで創作に踏み出せなかった人たちも挑戦しやすくなる。その結果、創作界隈の裾野が広がって、作家性のある人がどんどん登場して評価されるようになっていけばいいな、と思っています。
執筆:吉本幸記 編集:中田順子