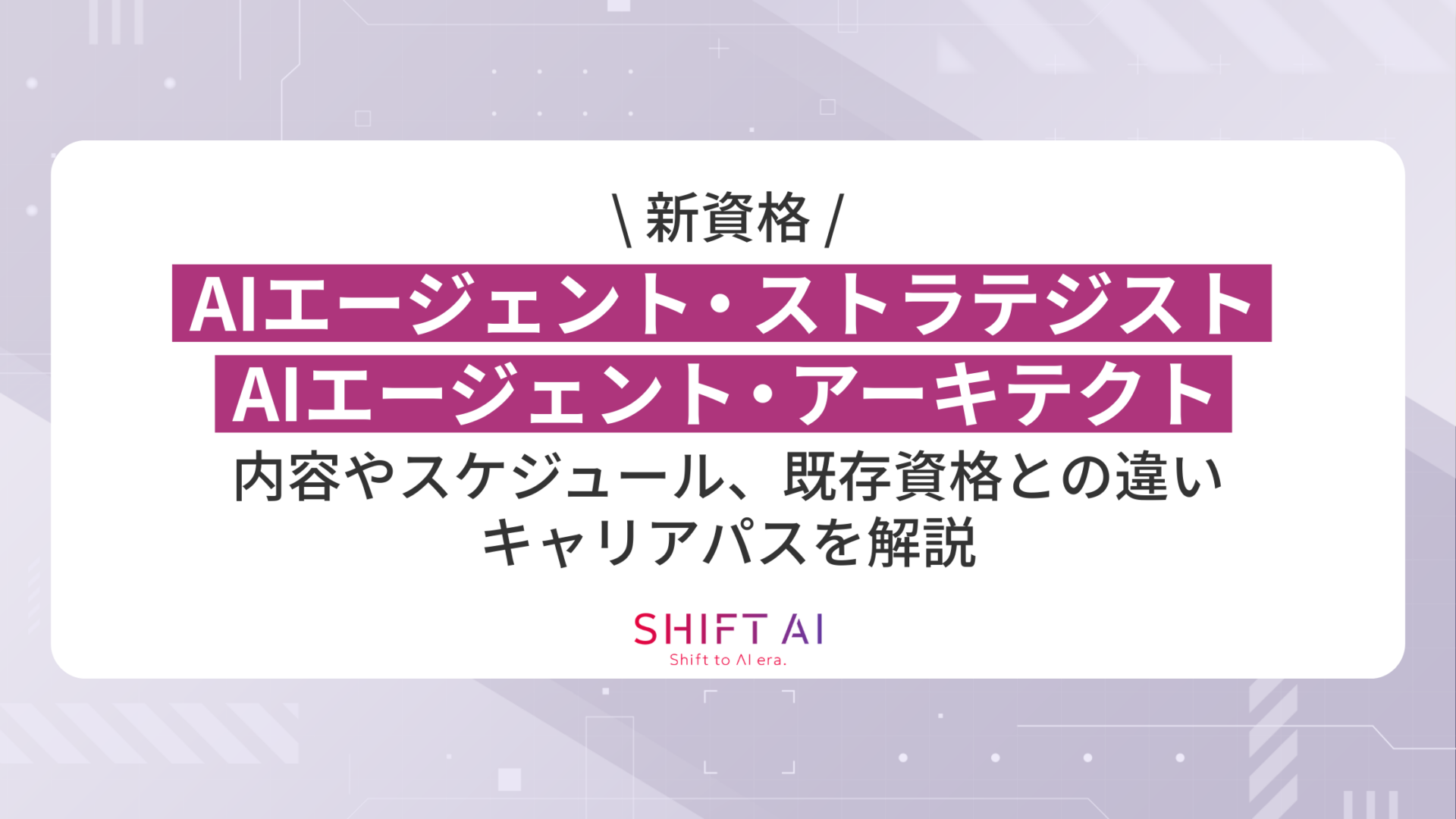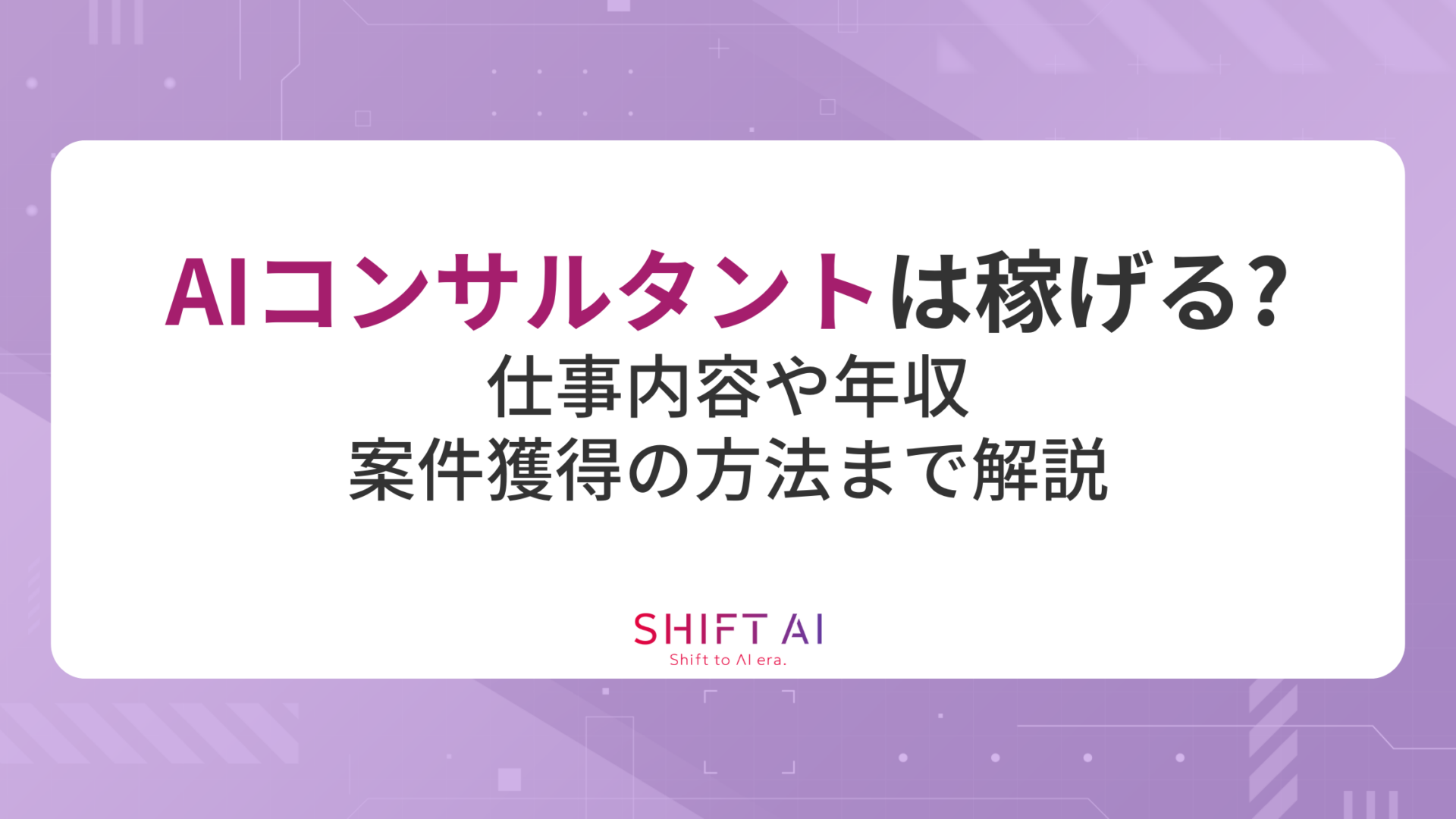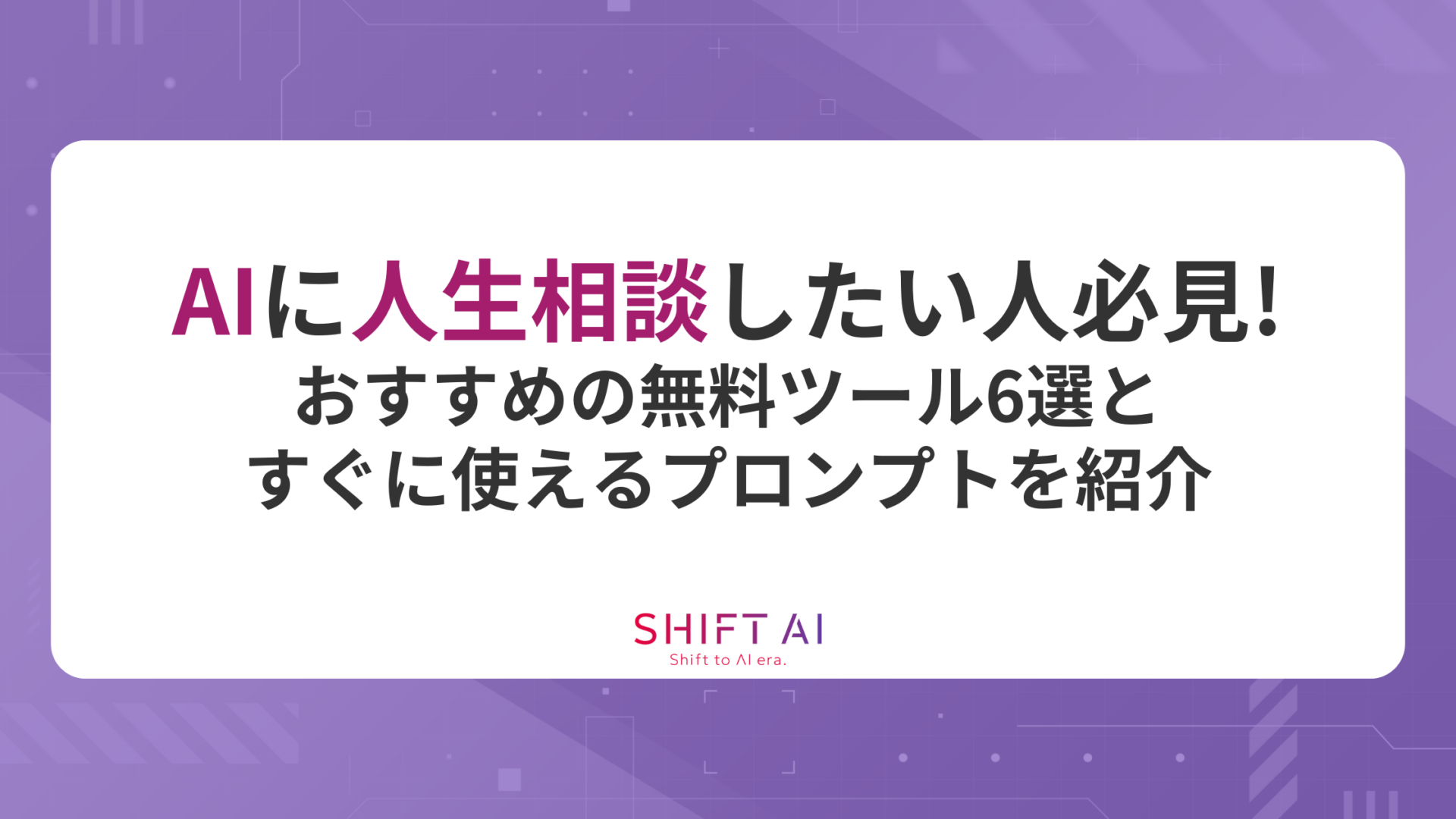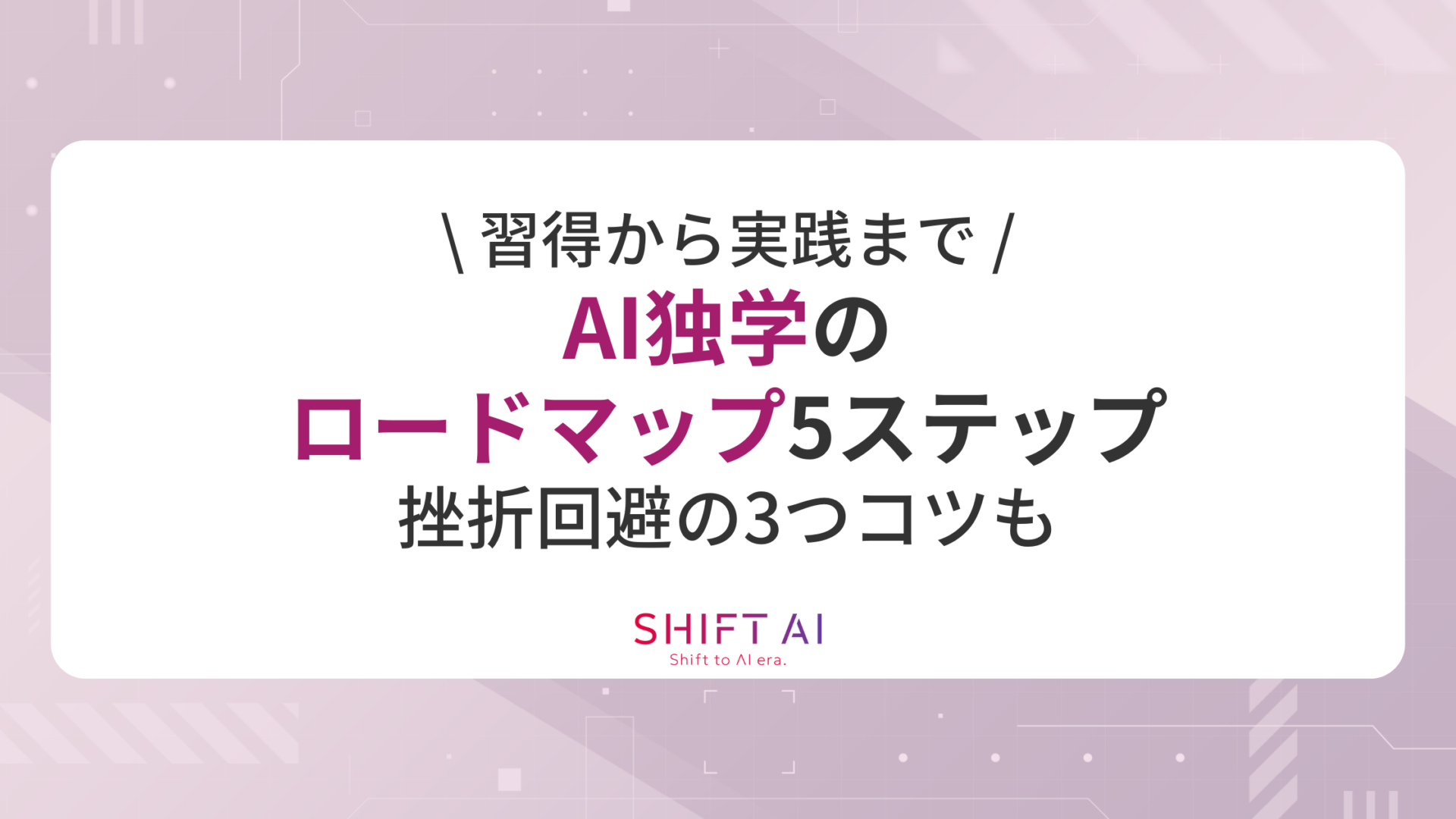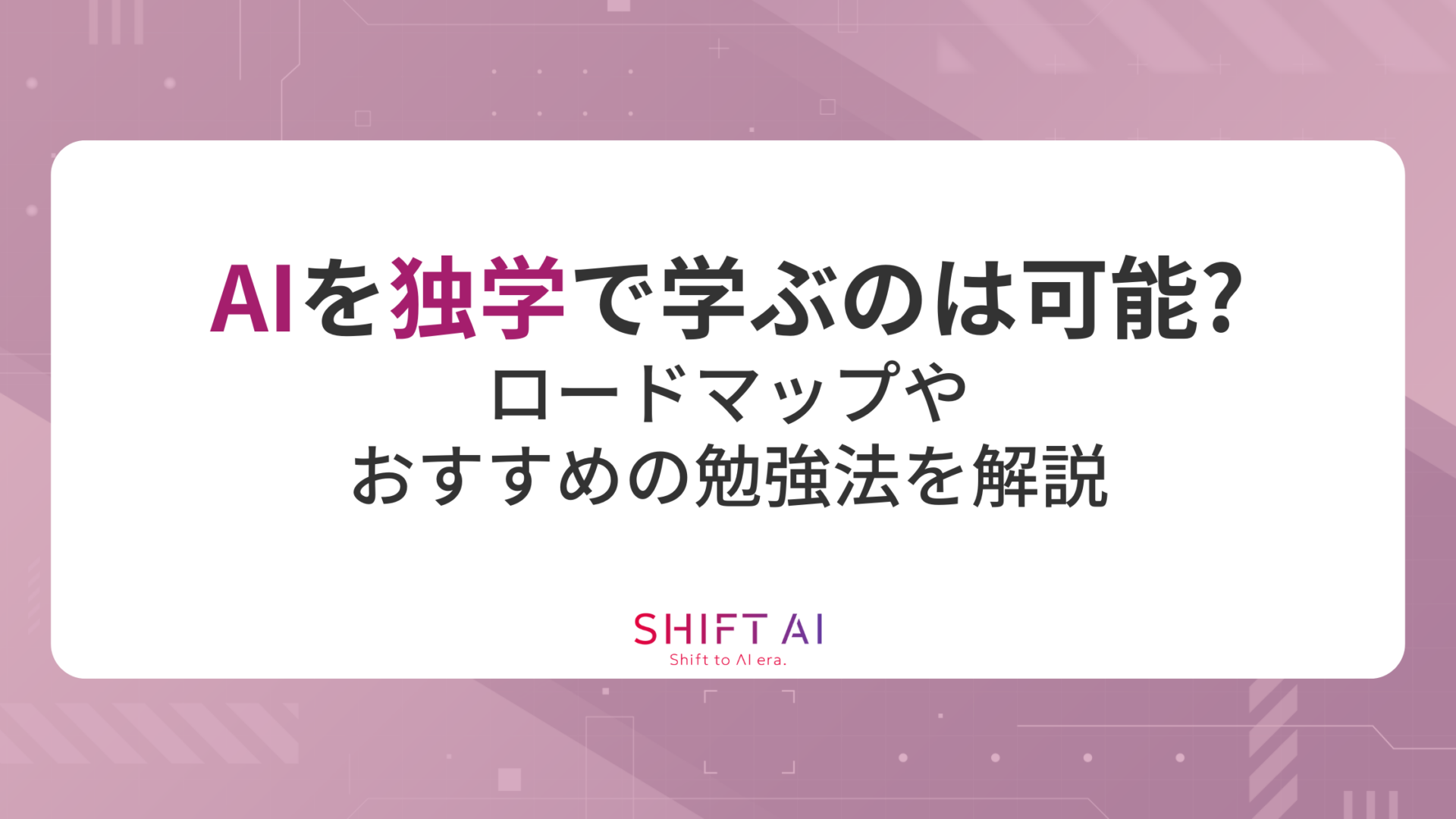文学賞に入選する時代へ。AI小説の進化と創作ツールの“いま”を読み解く

「AI」と聞くと、どこか難しくてとっつきにくい印象を抱く人も多いかもしれません。ですが、AIは私達の日常の様々な分野で応用されています。記事の前編では、公立はこだて未来大学所属の村井源教授にAIによる物語生成の現状と限界についてインタビューしました。
本稿では、前編に続き、日本と世界のAI生成小説の事例と、小説生成に特化した小説執筆支援AIを紹介します。
目次
10年の歩みで変わったAI小説。星新一賞の一次通過から最終選考へ
ChatGPTをはじめとする生成AIの登場によって、AIによる小説生成への関心が高まっています。しかし実は、その動きはChatGPT以前からすでに始まっていました。
2012年9月、公立はこだて未来大学の松原仁教授をリーダーにスタートしたのが、「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」。このプロジェクトでは、AIによるショートショートの創作に挑戦。
ショートショートの名手・星新一の作風を再現するため、1,000作を超える星新一作品の物語構造を、村井源教授が分析。構造のパターンを網羅した成果は、星新一公式サイト内のコラムでも公開されています。
この構造分析をもとに、2016年3月には成果発表会が開催され、AIによって生成された4本のショートショートを「星新一賞」に応募。そのうちの一部は一次審査を通過したものの、最終候補には残りませんでした。なお、応募作のうち3本は現在もオンラインで読むことができます。
その後、AI生成小説はさらに進化を遂げ、2025年2月に発表された第12回星新一賞では、AI小説家・青野圭司氏による『アルゴリズムの檻』が最終選考にまで残りました。同作の制作過程については、青野氏がnoteで詳しく記しており、「本文の約8割はAIが生成し、残りの2割を自身で推敲した」と語っています。
執筆当時(2024年9月)には、物語生成に優れたとされるClaude 3.5 sonnetを活用。生成された文章は、別の生成AIで分析しながら推敲を重ねたそうです。
また、2025年には、『東京都同情塔』で第170回芥川賞を受賞した作家・九段理江氏が、AIを用いた新たな創作でも注目を集めました。受賞直後の記者会見では「小説の5%をAIで書いた」と発言し話題に。さらに、博報堂発行の雑誌『広告』のリニューアル企画では、本文の95%をAIが執筆した短編小説『影の雨』を発表しています。
『影の雨』は約4,000字の短編ながら、制作にあたって入力されたプロンプトは20万字にのぼりました。九段氏によれば、「自分で書いた方が早く仕上がる」ものの、納得のいく出力を得るために膨大な試行錯誤を重ねたとのこと。作品とプロンプトの全文は、2025年6月20日に特設サイトで公開されました。
『影の雨』執筆におけるAIとの対話画面
(画像出典)https://www.hakuhodo.co.jp/magazine/116524/
中国の青少年向けSFコンテストで、AI小説が2位入賞
世界では、生成AIの登場以前から、小説をAIで制作しようとする試みが行われてきました。
1993年には、プログラマーのスコット・フレンチ(Scott French)氏が、『人形の谷』で知られる作家ジャクリーン・スーザンの文体をモデルに、AI生成小説『今度だけは(原題:Just This Once)』を発表。『今度だけは』を特集した1993年8月の Los Angeles Times によると、スコット・フレンチ氏はこの作品の制作に、4万ドルと8年の歳月を費やしたといいます。
それだけの時間がかかったのは、ジャクリーン・スーザンの文体を再現するために、フレンチ氏自身が彼女の作品を詳細に分析したためでした。こうして得られた分析結果は、ディープラーニング以前のAI技術であるルールベースAIに応用されています。
ChatGPTの公開以降、2023年5月にはAI生成小説『ある作者の死』(原題:Death of an Author)が発表されました。作中には架空の生成AI開発企業が登場し、題名やストーリー展開からも、生成AIを強く意識したメタフィクションであることがうかがえます。
『ある作者の死』の表紙。表紙イラストも生成AIで制作された。
(画像出典)https://www.pushkin.fm/audiobooks/death-of-an-author
イギリスメディア Metro が2023年5月に公開した記事によると、AI生成小説『ある作者の死』は、全体の95%が生成AIによる出力で構成されており、残りの5%を著者であるステファン・マルシェ(Stephen Marche)氏が執筆したといいます。制作には、ChatGPTと、後述する小説執筆支援AI「Sudowrite」が用いられました。両者に対して詳細なプロンプトを与えることで、平凡な出力を自身の文体に近づけたとされています。
2023年10月、中国で開催された文学賞「第5回江蘇省青少年科学普及SF作品コンテスト」において、AI生成小説『思い出の地』(中国語原題「机忆之地」)が2位を受賞。この件を報じた中国メディア・澎湃新聞の2023年10月の記事によると、同作品の作者は清華大学の沈陽教授でしたが、応募時にはAI生成による作品であることを明かしていなかったとのことです。
以上のコンテストでは、6人の審査員が応募作品を審査しましたが、『思い出の地』については、3人の審査員が高く評価しました。一方で評価しなかった審査員は、「AI生成かどうか」とは別に、単純にSF小説として受賞に値する水準に達していないと判断したといいます。
プロット生成やバッドエンドを生成する小説執筆支援AIが登場
ChatGPTのような汎用的な言語処理AIも小説執筆に活用されていますが、近年では小説執筆に特化した生成AIツールも数多く登場しています。
たとえば「AIのべりすと」は、日本語の小説生成に特化して訓練されたAIツール。使い方には、5〜6行程度の文章を入力してその続きを生成する「続きから」モードや、チャット形式で執筆を進める「チャットではじめる」モードなどがあります。
このツールは、EleutherAIが公開している言語AI「Mesh Transformer JAX」をベースにしており、最上位バージョンである「やみおとめ20B」は、約2テラバイト分の小説関連データを学習しています。
AIのべりすとのトップページ
(画像出典)https://ai-novel.com/index.php
日本語対応の小説執筆支援ツール「AI Buncho」には、好きなジャンルやキーワードを入力するとタイトルを生成する「タイトル生成」、12場面からなるプロットを生成する「プロット生成」、AIを相手としてリレー小説を執筆できる「AIリレー小説」などの機能があります。2024年4月には、リレー小説機能においてOpenAIモデルが使えるようになりました。
海外の小説執筆支援AIとしては、「sudowrite」がよく知られています。同ツールの「AIキャンバス」機能では、小説のプロットや登場人物の関係性を視覚的に整理することができます。また、「ブレインストーム」機能では、登場人物の名前や物語のタイトル案など、アイデアの候補を多数出力してくれます。
後継モデルの「Muse」は、生成AIが陥りがちな“平凡な文章ばかりになる”という弱点を克服し、より多様で洗練された出力が可能になっています。さらに、従来の生成AIがハッピーエンドを出力しがちだったのに対し、Museでは悲劇的な結末も描けるよう改良されています。
sudowriteの「AIキャンバス」画面
(画像出典)https://sudowrite.com/
以上のような小説執筆支援AIを活用したとしても、一流の小説を書き上げるには依然として多くの労力が必要です。こうしたツールは、執筆を効率化するだけでなく、ユーザーに多様な選択肢を提示することで、作品の品質向上を後押しする役割も果たしています。
ただし、その選択肢の中から最適な表現を選び取り、活かしていくには、ユーザー自身の労力と文芸的なセンスが欠かせません。
たとえば『影の雨』の制作秘話からもわかるように、現状の生成AIに高品質な小説を書かせようとすると、かえって人間が自分で執筆したほうが早い、という本末転倒な結果に陥ることすらあります。
それでも、執筆経験の少ない初心者にとっては、生成AIの力を借りることで、自力では踏み出せなかった小説制作の第一歩を、比較的容易に切り開ける可能性があります。
生成AIの登場は、こうした初心者を含む多くの人々に創作の機会を提供し、小説執筆をはじめとするさまざまな創作活動の裾野を広げることが期待されています。
記事執筆:吉本幸記 編集:中田順子